要注意!米国遺族年金は相続税対象?評価・計算方法
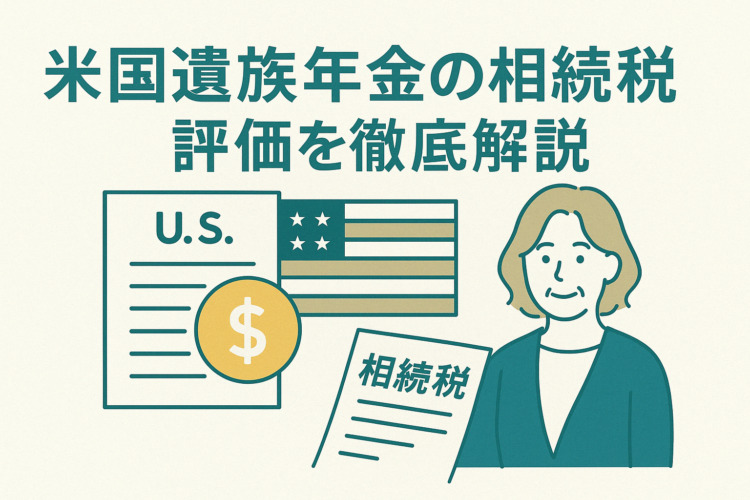
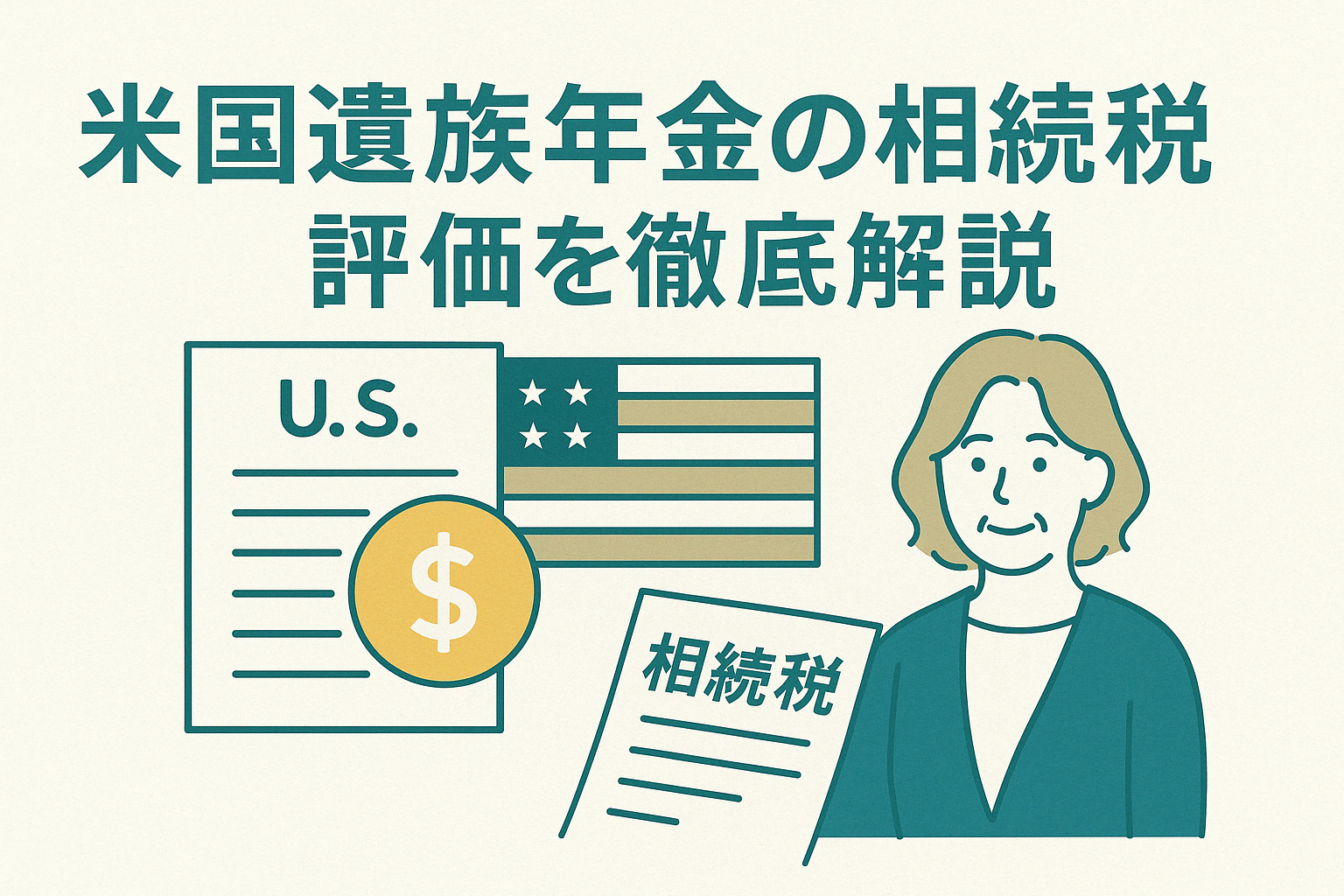
- 米国遺族年金は日本の相続税法上「契約に基づかない定期金に関する権利」として課税対象となる
- 米国遺族年金が相続税の対象となるかどうかの裁判が継続中のため将来的に課税関係が変わる可能性もある
- 評価方法は「終身定期金」として、複利年金現価率を用いて計算する
- 為替レートはTTB(対顧客電信買相場)を使用し、相続開始時点で換算する
- 予定利率は米国社会保障局の公表値を使用する必要がある
- 国際相続では日米租税条約に基づく外国税額控除を活用して二重課税を回避できる
近年、グローバル化の進展に伴い、海外に資産を有する方の相続事例が急増しています。
中でも米国遺族年金(Social Security Survivors Benefits)を巡る相続税問題は、専門家でも判断に迷う複雑なケースが少なくありません。
過去に米国駐在経験のある会社員が亡くなった場合には、必ず論点となるのがこの米国遺族年金となります。
本記事では、米国社会保障制度で支給される遺族年金が日本の相続税計算でどのように扱われるか、具体的な評価方法から実務上の注意点までを徹底解説します。
目次
米国遺族年金とは – 基本の理解
米国で生活していた方が亡くなった場合、その遺族は米国の社会保障制度に基づいて遺族年金(Survivors Benefits)を受け取ることができます。
この制度は日本の遺族年金と似ていますが、受給条件や金額の計算方法などが異なります。
特に日米間の相続が発生した場合、この米国遺族年金の受給権が日本の相続税の対象となるかどうか、またどのように評価すべきかについて、多くの方が疑問を持たれています。
国際化が進む現代社会において、海外に財産を持つ方や国際結婚をされている方にとって、この問題は非常に重要です。
米国社会保障制度における遺族給付の概要
米国の社会保障制度(Social Security)では、被保険者が亡くなった場合、その遺族に対して以下のような給付が行われます。
| 給付の種類 | 対象者 | 主な条件 |
| 遺族年金 (Survivors Benefits) |
配偶者、子供、両親など | 被保険者の死亡時に一定の条件を満たしていること |
| 一時金 (Lump-Sum Death Payment) |
配偶者または扶養子 | 被保険者と同居していたか、葬儀費用を負担したこと |
米国遺族年金の特徴として、受給権者の年齢や状況によって支給額や支給期間が異なる点が挙げられます。
例えば、配偶者の場合、60歳以上(障害がある場合は50歳以上)であれば受給資格があり、子供がいる場合はその年齢に関わらず受給できることがあります。
また、未婚の子供は18歳未満(全日制の学生は19歳まで、障害がある場合は年齢制限なし)であれば受給資格があります。
米国駐在経験がどのくらいあれば米国遺族年金をもらえるのか?
米国遺族年金を受給するための最低限必要な米国での就労期間は、基本的に以下のとおりです。
米国で最低6クレジット(約1年半相当)以上の社会保障税納付期間が必要
日米の年金加入期間を合算して合計40クレジット(10年相当)以上必要
ここでいう「クレジット」とは、米国社会保障制度における加入期間の単位で、1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当します。1年間で最大4クレジットまで取得可能です。
米国遺族年金と日本の相続税
日本の相続税法では、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、その死亡によって新たに発生する権利も課税対象となります。
米国遺族年金の受給権は、被相続人の死亡によって初めて発生する権利であり、日本の相続税法上は「みなし相続財産」として取り扱われます。
相続税法上の位置づけ
米国遺族年金の受給権は、相続税法第3条第1項第6号に規定される『契約に基づかない定期金に関する権利』に該当します。
相続税法第3条第1項次に掲げる場合においては、当該規定により取得したものとみなされる財産(第5号及び第6号においては、当該規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産)については、相続税を課する。
(中略)
六 相続又は遺贈により取得した生命保険契約に関する権利その他金銭の給付を目的とする契約に関する権利(第5号に掲げる権利を除く。)又は退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
この規定により、米国遺族年金の受給権は相続税の課税対象となります。
これに対し、日本の公的年金制度に基づく遺族年金は、国民年金法等の各年金の法律により非課税とされています。
米国遺族年金も日本の公的年金と同様の趣旨なのに相続税が課税されるのは不合理だということを理由に納税者が国税を訴えた事例があります。
その裁判は東京地方裁判所にてまだ継続中であり、結果は出ていません。
当該裁判の前に国税不服審判所で下された裁決が下記であり、納税者が負けてしまいました。
東京国税不服審判所令和5年12月1日非公開裁決
請求人は、①被相続人の死亡によりその配偶者が取得した米国の遺族年金(米国遺族年金)を受給する権利(本件受給権)は、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第6号に規定する相続により取得したものとみなされる財産に該当せず、相続税は課税されない旨を、また、②本件受給権は、仮に相続税の課税対象になるとしても、当該配偶者は相続開始日前に当該被相続人が受給していた米国の退職年金の50%相当額の家族年金を受給しており、相続開始日以後に当該退職年金と同額の米国遺族年金を受給することにより当該退職年金の50%相当額が増加したものであるから、米国遺族年金の50%相当額についてのみ、相続により取得したものとみなされる相続財産として課税されるべきである旨を主張する。しかしながら、本件受給権は、相続の効果として当該配偶者が当該被相続人から承継したものではなく、米国の連邦規則集の規定に基づき、当該被相続人の死亡により原始的に当該配偶者が取得したものであったと認められるから、相続税法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」に該当する。そして、米国遺族年金を受給する権利については、法令上、相続税が課税されないこととなる非課税規定は設けられていない。以上のことからすれば、本件受給権は、相続税法第3条第1項第6号に規定するみなし相続財産に該当し、相続税が課税される。また、米国の連邦規則集の規定に基づき、当該被相続人の死亡により、当該被相続人が受給していた米国の退職年金及び当該配偶者が受給していた家族年金の給付がいずれも終了し、当該配偶者が本件受給権を原始的に取得したのであるから、相続税法第3条第1項第6号に規定するみなし相続財産となるのは本件受給権の全部であって、その50%相当額ではない。(令5.12. 1 東裁(諸)令5-45)
今後裁判でどのような結論になるか現状では不明ですが、わかり次第この記事も更新していきます。
年金と相続税の詳しい解説は、年金にも相続税がかかる? 種類別にわかりやすく徹底解説!をご参照ください。
米国遺族年金と日本の公的遺族年金の比較
| 米国遺族年金 | 日本の公的遺族年金 | |
| 法的根拠 | 相続税法第3条第1項第6号 | 各年金法 (国民年金法、厚生年金保険法等) |
| 分類 | みなし相続財産 | 各年金法に基づく給付 |
| 相続税の課税 | 課税対象 | 非課税 |
| 課税理由 | 相続税法に非課税規定なし | 各年金法に非課税規定あり |
課税範囲 – 居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者
国際相続の場合、相続人の居住地や国籍によって課税範囲が異なります。
| 区分 | 定義 | 課税範囲 |
| 居住無制限 納税義務者 |
日本国内に住所を有する者 | 全世界の 財産に課税 |
| 非居住無制限 納税義務者 |
日本国内に住所はないが、日本国籍を有し、 相続開始前10年以内に日本に住所を有していた者 |
全世界の 財産に課税 |
| 制限納税義務者 | 上記以外の者 | 日本国内の 財産のみ課税 |
この区分に従うと、日本に住所がある相続人や、日本国籍を持ち10年以内に日本に住所があった相続人が米国遺族年金の受給権を取得した場合、その全額が日本の相続税の課税対象となります。
国際相続の場合の納税義務判定や課税財産の範囲のより詳しい解説は下記コラムをご参照ください。
国際相続における相続税の納税義務の判定を徹底解説!
【国際相続】国内財産、国外財産の判定をわかりやすく徹底解説
米国遺族年金の評価方法
米国遺族年金は相続税の課税対象となりますが、その評価方法について詳しく見ていきましょう。
遺族年金は将来にわたって定期的に受け取る権利であるため、相続開始時点での評価額(現在価値)を計算する必要があります。
終身定期金としての評価
米国遺族年金の受給権は、相続税法上、終身定期金として評価されます。
終身定期金の評価方法は、相続税法第24条第1項に規定されており、以下の3つの金額のうち最も高い金額で評価します。
| 評価方法 | 内容 |
| 1. 解約返戻金 | 当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額 |
| 2. 一時金 | 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合の当該一時金の金額 |
| 3. 複利年金現価 | 年金受給者の余命年数に応じ、年間平均受給額に複利年金現価率を乗じた金額 |
米国遺族年金の場合、通常、解約返戻金や一時金の給付はありませんので、実質的には3番目の「複利年金現価」による評価が適用されます。
複利年金現価の計算方法
複利年金現価の計算は次の手順で行います。
評価額 = 1年当たりの平均額 × 複利年金現価率
この計算に必要な要素を一つずつ確認していきましょう。
1. 1年当たりの平均額の算出
米国遺族年金は通常、毎月一定額が支給されます。
1年当たりの平均額を算出するには、月額 × 12ヶ月で計算します。
ただし、米国遺族年金は物価変動により受取額が変わるため、相続開始日時点での受取額を基準とします。
また、米ドルで受け取る年金は、相続開始時のTTB(対顧客電信買相場)レートで円に換算します。
1年当たりの平均額 = 1,000ドル × 12ヶ月 × 140円 = 1,680,000円
2. 複利年金現価率の決定
複利年金現価率は、以下の3つの要素から決定されます。
| 要素 | 内容 | 確認方法 |
| 受給者の 生年月日・性別 |
余命年数を決定する基礎情報 | 相続人の情報より確認 |
| 余命年数 | 相続開始時点における 受給者の平均余命 |
相続開始日時点の 完全生命表より確認 |
| 予定利率 | 将来の年金価値を現在価値に 割り引く際の利率 |
米国社会保障局の公表値(Effective率)を使用 |
※相続開始年の米国社会保障局の公表値(Effective率)が公表されていない場合には直近の利率を採用します。
3. 具体的な計算例
事例を使って具体的な計算例を見てみましょう。
・相続開始日:令和7年2月19日
・受給者:昭和30年5月15日生まれの女性
・受給額:月額1,200ドル
・相続開始時の為替レート:1$=151.14円(TTB)
・予定利率:米国社会保障局の公表値により2.5%
【計算過程】
1. 1年当たりの平均額の計算
1,200ドル × 12ヶ月 × 151.14円 = 2,176,416円
2. 余命年数の確認
相続開始日時点の完全生命表より → 21年
3. 複利年金現価率の計算
計算結果 → 16.185(国税庁HP「定期金に関する権利の自動計算」ツールにて計算)
4. 複利年金現価の計算
2,176,416円 × 16.185 = 35,225,292円
この例では、月額1,200ドルの米国遺族年金受給権の評価額は約3,522万円となります。
この金額が相続財産に加算され、相続税の計算基礎となります。
なお、上記米国遺族年金受給権の評価額は国税庁HP 定期金に関する権利の自動計算に必要情報を入力していけば自動で計算が可能です。
相続税の計算と二重課税への対応
米国遺族年金の受給権が相続財産に加算されると、日本の相続税が課税されますが、同時に米国でも相続税(Estate Tax)が課税される可能性があります。
このような国際間の二重課税を調整するため、外国税額控除の制度があります。
外国税額控除の仕組み
外国税額控除とは、外国で課された相続税等について、一定の限度額まで日本の相続税から控除できる制度です。
控除限度額 = 日本の相続税額 × 外国で課税される財産の価額 ÷ 相続税の課税価格の合計額
つまり、日本の相続税のうち、外国財産に対応する部分について、外国で納付した税額を控除できる仕組みです。
ただし、控除限度額を超える部分については控除できません。
日米間の二重課税調整
日本と米国の間では、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(日米租税条約)が締結されています。
この条約に基づき、両国間での相続税の二重課税問題が調整されますが、米国遺族年金の受給権に関しては注意が必要です。
| 状況 | 対応 |
| 米国でも相続税が課税された場合 | 外国税額控除を申請して二重課税を調整 |
| 米国で相続税が課税されない場合 | 日本の相続税のみ納付 |
米国の遺族年金に対する相続税の取り扱いは日本と異なる場合があります。米国では相続税(Estate Tax)の基礎控除額が高額(2020年時点で約1,180万ドル)であるため、多くの場合、米国の相続税は課税されない可能性があります。
相続税の外国税額控除の詳しい解説は、相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
相続税の申告と納付
米国遺族年金を含む国際相続の場合、相続税の申告と納付に関して特に注意すべき点があります。
申告期限と必要書類
相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
国際相続の場合、外国にある財産の評価や外国税額控除の計算などに時間がかかることがあるため、事前の準備が重要です。
これらの書類の入手には時間がかかることがあるため、早めに準備を始めることをお勧めします。
専門家の活用
国際相続、特に米国遺族年金の評価や外国税額控除の計算は複雑なため、国際税務に精通した税理士や相続専門家に相談することをお勧めします。
特に以下のような場合は専門家のサポートが不可欠です。
| 状況 | 対応 |
| 米国と日本の両方で相続税が課税される場合 | 外国税額控除の最適化が必要 |
| 米国の遺族年金以外にも海外財産がある場合 | 全体的な相続対策が必要 |
| 相続人が複数の国に居住している場合 | 各国の税法に基づく複雑な調整が必要 |
よくある質問(Q&A)
Q1: 米国遺族年金は全額が相続税の対象になりますか?
はい、米国遺族年金の受給権全額が相続税の対象となります。
日本の公的年金制度による遺族年金とは異なり、米国の遺族年金は相続税法上の非課税規定の適用がありません。
ただし、受給権の評価額は将来にわたって受け取る年金の現在価値として計算されるため、実際に受け取る総額とは異なります。
Q2: 米国遺族年金を受け取っていますが、毎年の所得税はどうなりますか?
米国遺族年金は所得税の課税対象となります。
日本居住者の場合、雑所得として確定申告が必要です。
ただし、日米租税条約により一定の軽減措置が適用される場合があります。
また、米国でも課税される可能性があるため、二重課税の調整が必要になることがあります。
所得税に関しては外国税額控除を利用することで、国際間の二重課税を調整できます。
Q3: 相続開始後に米国遺族年金の受給額が変更された場合、相続税の再計算は必要ですか?
原則として不要です。
相続税の評価額は相続開始時点での状況に基づいて計算されるため、その後の受給額の変更があっても相続税の再計算は必要ありません。
ただし、相続開始時点での受給権の内容に誤りがあった場合(例:計算ミスなど)は、修正申告が必要になることがあります。
Q4: 米国遺族年金の受給権を放棄することはできますか?その場合、相続税はどうなりますか?
米国遺族年金の受給権を放棄することは可能です。
受給権を放棄した場合には相続または遺贈により取得した財産とはみなされないため相続税の対象にはならないと考えます。
ただし、特定の状況下では例外もあるため、具体的なケースについては税務専門家に相談することをお勧めします。
まとめ – 米国遺族年金の相続税対策
米国遺族年金は日本の相続税法上、「契約に基づかない定期金に関する権利」として課税対象となります。
その評価方法は終身定期金として、複利年金現価率を用いて計算されます。
具体的には、年間の受給額(TTBレートで円換算)に、受給者の余命年数に応じた複利年金現価率を乗じることで評価額を算出します。
国際相続の場合は二重課税の問題も生じるため、外国税額控除制度を活用して税負担を適正化することが重要です。
米国遺族年金を含む国際相続は複雑なため、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じることをお勧めします。
適切な準備と対策により、不必要な税負担を避け、スムーズな相続手続きを実現できるでしょう。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00







