相続時精算課税制度をわかりやすく徹底解説(令和5年改正論点更新)
相続時精算課税制度とは、読んで字の如く、「過去の贈与を相続のときにすべて精算するよ」という贈与制度の一つです。
贈与制度はこの相続時精算課税と暦年贈与の二つの制度があります。
暦年贈与は亡くなる前3年間(令和6年1月1日以降の贈与については7年間)の贈与のみを相続時に精算しますが、相続時精算課税制度は過去の贈与のすべてが精算の対象のため10年以上前の贈与であっても相続時に相続財産に加算する必要があるのです。
なお、令和6年1月1日以降の贈与については精算課税であっても年間110万円の基礎控除が創設され、当該基礎控除については加算不要となりました。
したがって、令和6年1月1日以降はケースによっては暦年課税よりも相続税の節税に繋がる可能性があるため精算課税適用者が増加することが予想されます。
精算課税の概要をしっかり理解してできるだけ多くの財産を効率的に次世代に繋げられるようにしましょう。
精算課税の全体像を直近の改正点も含めてわかりやすく詳細に解説していきます。
是非最後までご確認ください。
目次
1. 精算課税精度の使い勝手が大幅に改善!(令和5年度税制改正まとめ)
令和5年度税制改正により相続時精算課税制度が大幅に見直されました。
主な改正点は下記の通りです。
(1)110万円基礎控除の創設
(2)土地又は建物が被災した場合の加算額の修正
(1)110万円基礎控除の創設
①改正内容
暦年課税贈与については少額不追求の観点から年間110万円の基礎控除が設けられています。
すなわち、年間110万円までは贈与税がかからず、贈与税申告も必要ないのです。
これに対し、精算課税贈与を選択した後は10,000円であっても贈与した場合には贈与税の申告が必要であり、全額相続税のときに相続財産に加算が必要でした。
したがって、精算課税贈与は原則として相続税の節税にはならないとされていたのです。
相続税の節税に繋がらないため相続時精算課税を選択する人が少なかったのです。
このような問題点?を解決するために令和5年税制改正で110万円の基礎控除が設けられることになりました。
この精算課税の110万円の基礎控除は暦年課税の基礎控除とは別物です。金額も名前も同じなので分かりづらいですが。。。
すなわち、年間110万円までは精算課税を選択したとしても贈与税の申告が不要となったのです。
さらに、精算課税を選択した後は年間110万円までは相続財産に加算しなくてもよくなったのです。
暦年課税の場合には亡くなる前7年間(改正前は3年間)の贈与は110万円以下であっても相続財産に加算する必要がありますが、精算課税を選択すれば年間110万円までは相続財産に加算しなくても良いのです。
したがって、暦年課税よりも相続時精算課税を選択した方が節税になるケースが多くなったということです。
国の狙いとしても暦年贈与よりも精算課税を有利にして富裕層は皆精算課税にしてもらいたいという思惑があるのだと思います。
改正後の精算課税贈与の計算式は下記の通りです。
②施行時期
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。
Q&A
A 110万円以下であるため贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税選択届出書の提出は必要なので注意してください。
A ご指摘の通り精算課税贈与の基礎控除と暦年贈与の基礎控除は別枠ですので異なる人から異なる贈与を受ければ年間220万円まで非課税となります。
A 父も母も精算課税贈与を選択した場合には合計で110万円までしか非課税になりません。
基礎控除110万円を下記の算式で按分して計算することとなります。
110万円 ✕ 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格 / 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額
したがって、父と母の二人から110万円の贈与を受けた場合には、父で55万円、母で55万円をそれぞれ控除した金額が精算課税贈与の対象となります。
もちろん、基礎控除を超過しているため贈与税の申告も必要となります。
なお、2,500万円の特別控除額の範囲内であれば贈与税はかかりません。
その10年後に父から贈与を受けた土地が1,200万円であることが判明しました。
当初の贈与税申告では基礎控除を父55万円、母55万円で計算していましたが、土地の評価が変更したことにより基礎控除も修正したほうが良いでしょうか。
A 修正する必要はありません。
修正する必要がある場合のあるべき基礎控除は下記になるかと存じますが修正は不要となります。
父 110万円✕1,200万円/(1,200万円+1,000万円)=60万円
母 110万円✕1,000万円/(1,200万円+1,000万円)=50万円
除斥期間が経過してしまった場合には基礎控除の修正は不要である根拠としては、下記国税庁質疑応答事例となります。
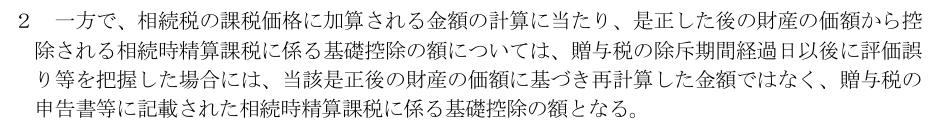 国税庁HP 相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係) について(情報)
国税庁HP 相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係) について(情報)
なお、父が亡くなったときに父の相続財産に加算する金額は、本体の評価額は是正後の金額で基礎控除は是正前の金額となり、具体的には下記の通り計算します。
1,200万円(是正後)-55万円(是正前)=1,145万円
(2)土地又は建物が被災した場合の加算額の修正
①改正内容
相続時精算課税により贈与した財産についてどんなに価値が減少しようが相続時には贈与時の相続税評価額で相続財産に加算する必要があります。
例えば、1,000万円の相続税評価額の建物を精算課税により贈与して、その後建物が火災により滅失して価値がゼロになったとします。その後贈与者である親が亡くなり、相続税を計算するときに既に滅失している建物にも関わらず1,000万円を相続財産に加算する必要があるということです。
このような不合理な部分も精算課税が広まらなかった一因です。
この不合理な部分について令和5年度税制改正で一部是正されました。
改正内容としては、精算課税による贈与を受けた土地又は建物につき災害によって相当の被害を受けた場合には、その被害を受けた部分を贈与財産の価額から控除できるという特例です。
②施行時期
令和6年1月1日以後に、土地又は建物が災害により被害を受ける場合について適用されます。
なお、令和6年1月1日前に相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した土地又は建物について、令和6年1月1日以後に災害により被害を受ける場合についても適用可能です。
以上、精算課税に関する令和5年度税制改正の解説でした。
なお、令和5年度税制改正の相続関連のまとめの解説については、生前贈与は7年が相続税の対象へ! 令和5年(2023年)税制改正速報をご参照ください。
2. 相続時精算課税制度のわかりやすい解説!
(1)適用対象者
精算課税制度の適用を受けることのできる者は、下記の通りです。
受贈者:18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫
Q&A
A 贈与の年の1月1日時点で上記年齢以上である必要があります。
A 贈与者の相続人のうち最も先順位の相続権(代襲相続権を含む)のある人です。
A ひ孫は適用できません。ただし、代襲相続人であるひ孫であれば適用可能です。
A 適用できません。義父と養子縁組をした場合には直系卑属である推定相続人になりますので適用が可能となります。
A 贈与日現在で判断します。
A 養子でも適用可能です。したがって、養子の場合には養親、実親の両方で精算課税の適用が可能ということです。
A 相続時精算課税において養子の数の制限はありませんので何人目の養子であっても適用可能です。
なお、基礎控除、相続税の総額の計算、生命保険の非課税枠等については養子の数に制限があるためご注意ください。
相続税と養子縁組の関係についての詳しい解説は、【養子縁組で相続税対策】パターンごとのトラブル対処法を紹介をご参照ください。
A 養子縁組解消しても引き続き精算課税の適用は可能です。
(2)特別控除額
精算課税の特別控除額(非課税枠)は、2,500万円となります。
令和5年度税制改正で創設された基礎控除110万円とは別枠で2,500万円の特別控除額が設けられているということです。
Q&A
A 1年単位ではなく一生涯で2,500万円が上限です。
A 2,500万円の特別控除額は期限内申告の場合にのみ適用が可能です。したがって、期限後申告の場合には贈与額に20%を乗じた贈与税を収める必要があります。
(3)適用対象財産
相続時精算課税制度の適用対象財産には制限はありません。
したがって、不動産、現預金、有価証券、非上場株式、金銭債権等どのような財産を贈与しても適用が可能です。
Q&A
A 相続税申告の場合の評価と同様に相続税評価を採用します。
A 小規模宅地等の特例は、贈与税申告では適用できません。
(4)税額計算
基礎控除110万円と特別控除額2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算します。
計算方法は下記の通りです。
暦年贈与のような累進税率ではありません。
Q&A
A 精算課税贈与の申告をしたとしても住民税は別途かかりません。
A 不動産を贈与した場合には登録免許税や不動産取得税がかかるケースがあります。
(5)申告手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、精算課税による贈与を受けた最初の年の翌年の確定申告期限までに税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
また、精算課税の適用ができる受贈者の要件を満たすかどうかを判定するために受贈者(子や孫)の戸籍の謄本又は抄本や贈与者(父母や祖父母)の戸籍の謄本又は抄本の添付が必要となります。
Q&A
A 暦年贈与同様に年間110万円以下であれば申告は不要です。なお、申告は不要ですが相続時精算課税選択届出書の提出は必要なので注意しましょう。
A 精算課税を選択してしまうと暦年贈与には一生戻れません。選択する際は慎重に判断しましょう。
A できません。
同一の者から同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることはできず、精算課税贈与の選択をした場合には必ず1月1日から選択したことになります。
例えば、令和7年2月1日に暦年贈与110万円、その後精算課税の選択をして令和7年10月1日に精算課税贈与110万円ということはできずに2月1日にした贈与も精算課税贈与に該当することとなります。
A 年の途中で養子になった場合には同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることが可能です。
例えば、下記のケースを想定してみましょう。
令和7年2月1日:110万円贈与
令和7年5月10日:養子縁組
令和7年10月15日:500万円贈与
上記の場合には110万円については暦年贈与、養子縁組後の500万円については精算課税贈与とすることが可能です。
A 精算課税は贈与者ごとに選択できますので祖母からの贈与は暦年贈与のままでも大丈夫です。もちろん、祖父からも祖母からも精算課税贈与とすることもできます。
A 受贈者(子、孫)の住所地を所轄する税務署です。
A 下記の区分に応じた期限となります。
①贈与税申告期限前に相続税申告期限が到来する場合:相続税申告期限までに選択届出書を提出
②相続税申告期限前に贈与税申告期限が到来する場合:贈与税申告期限までに選択届出書を提出
(6)相続税申告
精算課税贈与を受けた後にその贈与者が死亡した場合には、贈与者の相続財産に基礎控除110万円を超えた金額を加算する必要があります。
計算の結果、相続税<贈与税だった場合には、過去に納めた贈与税の一部が還付されます。
Q&A
A 贈与時点の評価額を採用します。
その他の評価時点の詳しい解説は、遺産分割、相続税申告、特別受益、遺留分、生前贈与加算などの評価基準日(評価時点)を徹底解説はご参照ください。
なお、土地又は建物の贈与を受けた場合において災害により被害を受けた場合には一定の控除が可能となります。
A ご指摘の通り、暦年贈与は相続又は遺贈により財産を一切取得していない場合には3年間(令和6年以降は7年間)の贈与を持ち戻す必要はありません。
詳しくは、【令和6年の贈与から】亡くなる前7年以内の贈与は相続税の対象へをご参照ください。
これに対し、精算課税贈与は相続又は遺贈により財産を一切取得していなかったとしても過去に受けた精算課税贈与を相続財産に加算する必要があります。
A 暦年贈与の100万円は相続財産に加算する必要があります。
根拠としては、相続税法基本通達19-11(注書き)となります。
A 精算課税制度により贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はできません。
A 相続時精算課税の適用を受けた者が債務控除の適用を受けることができるかどうかは、下記の通り状況により異なります。
(1)相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者
①相続人又は包括受遺者
債務控除OK
※制限納税義務者の場合には一定の公租公課等の相続税法第13条第2項に掲げる債務のみ
②相続人以外の特定受遺者(特定遺贈を受けた被相続人の孫や相続放棄をして生命保険金を受け取った相続人など)
債務控除NG
(2)相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者
①相続人
債務控除OK
※相続開始の時において日本に住所がない者の場合には一定の公租公課等の相続税法第13条第2項に掲げる債務のみ
②相続人以外
債務控除NG
債務控除の詳しい解説は、【相続税申告】債務控除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
A 代襲相続人に該当しなければ2割加算の対象になります。
相続税については、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)及び配偶者以外の人が財産を取得した場合にはその相続税につき20%の加算が必要となります。
2割加算についての詳しい解説は、相続税の2割加算についてわかりやすく徹底解説!をご参照ください。
A 相続開始時に代襲相続人に該当するため、2割加算の対象にはなりません。
贈与時に2割加算対象者であったとしても相続開始時に2割加算対象者でなくなっている場合には2割加算の必要はありません。
A 2割加算の対象とはなりません。
相続開始時に2割加算の対象となる人であっても精算課税贈与を受けた時に被相続人の一親等の血族であった場合にはその贈与財産については2割加算の対象とはなりません。
A 更正の請求の期限を徒過しているため還付の請求はできません。納税した相続税の更正の請求の期限は、ご指摘の通り、相続税の申告期限から5年ですが、精算課税の贈与税の還付を受けるための更正の請求期限は相続開始日から起算して5年までとなります。すなわち、本件の場合だと令和4年1月までに還付しないといけませんでした。
A 確かに贈与税の除斥期間が経過しているため精算課税贈与の期限後申告は今からしても受け付けてもらえません。ただし、10年前の500万円の贈与は相続財産に加算する必要があります。
なお、暦年贈与の場合には贈与が成立していれば10年前の贈与は贈与税申告をしていなかったとしても相続財産に加算する必要はありません。
A 精算課税贈与の申告の修正は確かに受け付けてもらえませんが、相続税申告では今回適切に計算した贈与時の評価額を採用します。したがって、除斥期間が経過した精算課税贈与の評価額が誤っていた場合には贈与税申告書に記載された評価額は訂正できませんが、相続税申告時に改めて適切な評価額にて計算し直す必要があります。
A 税務署に対して過去の申告書等を確認する手続きとしては、下記の二つがあります。
①申告書等閲覧サービス
②個人情報開示請求
または、他の相続人に相続税法49条の開示請求をしてもらう方法もあります。
詳しくは、生前贈与がある場合の相続税申告 ■贈与税の申告内容の開示をご参照ください。
A できません。
A できます。
精算課税贈与でも暦年贈与でも相続財産の課税価格に算入された財産を譲渡した場合には取得費加算の特例の適用が可能です。
もちろん、贈与を受けた財産を相続税申告前に譲渡したとしても取得費加算の特例は適用できません。
取得費加算の特例についての詳しい解説は、相続税の取得費加算の特例をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
A 平成20年当時は住宅取得資金贈与については特例的に精算課税の特別控除額を1,000万円上乗せできるという制度(旧措置法70の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))がありました。この制度は平成21年12月31日までで廃止されています。
したがって、今回の相続税申告で相続財産に加算すべき金額は2,500万円ではなく3,500万円となります。
当時の申告書を紛失した場合や1,000万円の上乗せか住宅取得資金の非課税かの判別が難しい場合には、前述の相続税法49条の開示請求をすれば確実に相続財産に加算すべき金額が判明するでしょう。
旧措置法70の3の2(住宅取得資金特別控除の特例)に似た制度として租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)というのがあります。
こちらは、現行制度であり廃止されていませんが、60歳未満の直系尊属であっても住宅取得資金なら精算課税の適用をしても良いよという制度になります。
住宅取得資金贈与の3つの制度を改めてまとめます。
| 措置法70条の2 (住宅取得等資金の非課税) |
措置法70条の3 (相続時精算課税選択の特例) |
旧措置法70の3の2 (住宅取得資金特別控除の特例) |
|
| 制度の内容 | 一定金額まで非課税で贈与できる | 60歳未満でも住宅取得資金を精算課税で贈与できる | 精算課税贈与に1,000万円上乗せできる |
| 精算課税 OR 暦年贈与 |
暦年贈与 | 精算課税 | 精算課税 |
| 非課税枠 | 省エネ等住宅:1,000万円 上記以外:500万円 |
2,500万円 | 1,000万円 (精算課税と合わせれば3,500万円) |
| 相続財産への加算 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 適用期間 (いつの贈与から(まで)適用できるのか) |
平成21年創設 現行制度 |
平成15年創設 現行制度 |
平成15年創設 平成21年末廃止 |
A 60歳未満でも精算課税贈与が可能です。
3. メリット・デメリット
相続時精算課税制度のメリットとデメリットを確認しましょう。
| メリット | デメリット |
□令和6年1月1日以降は基礎控除110万円が創設され贈与税申告も不要で相続財産に加算も不要 □一度に多額の贈与ができる □収益を生む財産を贈与した場合には贈与後の収益が受贈者に帰属するため相続税の節税になる □将来値上がりする財産を贈与した場合には相続税の節税になる □将来相続税が基礎控除以下の場合には早期に財産を移転できるし税負担が増加することもない |
□暦年贈与に戻れない □贈与した財産が値下がりした場合に相続税の負担が重くなる □受贈者が先に死亡した場合に税負担が重くなる □贈与財産は小規模宅地等の特例の適用ができない □相続に比べ流通税(不動産取得税、登録免許税)負担が重くなる |
4. 暦年贈与との比較
暦年贈与と精算課税贈与の比較をしましたので是非ご確認ください。
| 暦年贈与 | 精算課税贈与 | |
| 贈与者 | 制限なし | 60歳以上の父母又は祖父母 |
| 受贈者 | 制限なし | 18歳以上の直系卑属である 推定相続人又は孫 |
| 基礎控除 | 年間110万円 | 年間110万円 |
| 特別控除額 | なし | 一生涯2,500万円 |
| 税率 | 10%~55%の累進税率 | 一律20% |
| 非課税枠以下の申告義務 | 申告不要 | 申告必要 |
| 届出義務 | 不要 | 相続時精算課税選択届出書 が必要 |
| 相続財産に加算する金額 | 3年間のみ(令和6年以降の贈与は7年間) ※110万円以下であっても加算必要 |
過去の贈与すべて ※令和6年以降は110万円以下は加算不要 |
| 受贈者が先に死亡 | 特に論点なし | 受贈者の相続人が承継 |
| 贈与税額控除 | 還付なし | 還付あり |
| 相続開始年 の贈与 |
相続財産に加算 (相続又は遺贈により財産を取得していない人は贈与税申告) |
相続財産に加算 ※令和6年以降は110万円以下は加算不要 |
暦年贈与と精算課税の有利判定の解説は、暦年贈与と精算課税はどちらが有利? フローチャートで解説!をご参照ください。
5. 相続時精算課税贈与を適用すべきケース
デメリットやリスクが多い相続時精算課税制度ですが適用したほうが良いケースを最後にまとめて終わりにしたいと思います。
逆に下記に該当しない人は精算課税贈与を適用しないほうが良いでしょう。
(1)7年以内に相続が発生しそうな場合
税制改正により暦年贈与の加算対象期間が7年間になりました。
これに対し、精算課税を選択すれば110万円以下の贈与であれば相続開始前7年間であっても相続財産に加算しなくても良いのです。
ということは7年以内に相続が発生しそうな場合には精算課税を選択したほうが明らかに有利でしょう。
(2)年間110万円の贈与でも十分に相続税の節税効果が高い場合
相続発生まで7年以上ありそうでも財産の規模的に年間110万円以下の贈与でも相続税の節税効果が高いような人は精算課税を選択しても良いでしょう。
これに対し、5億円を超えるような財産がある人で相続発生まで7年以上ありそうな人は精算課税を選択しないで暦年贈与をした方が有利になる可能性が高いです。
贈与税の税率と相続税の税率の差を活用して贈与税を払ってでも次世代に財産を移転したほうが最終的な手残りが多くなるでしょう。
一度シミュレーションを税理士に依頼してみてもいいかもしれません。
(3)将来の相続税が基礎控除以下で早期に財産を移転したい場合
将来の相続税が基礎控除となることが見込まれている場合で、かつ、早めに財産を子や孫世代に移転したい場合には、精算課税贈与が最適でしょう。
暦年贈与の場合には110万円までしか無税で一度に移転できませんが、精算課税贈与であれば2,500万円もの財産を無税で次世代に移転できます。
(4)将来確実に値上がりする財産を保有している場合
将来確実に値上がりするなんてことはわかりませんが、もしそのような財産がある場合には精算課税贈与を活用すれば相続税の節税に繋がります。
例えば、贈与時に3,000万円、相続時に5,000万円の財産を贈与せずに相続のときに移転した場合には当然5,000万円に相続税が課税されますが、精算課税贈与をしておけば3,000万円に相続税が課税されるため、ある意味評価額を固定化できるのです。
逆に値下がりする財産を精算課税贈与をするのはご法度です。
(5)収益を生む財産を保有している場合
家賃を生む賃貸不動産や配当がある有価証券を贈与した場合には贈与後の収益が受贈者に帰属するため相続税の節税に繋がります。
すなわち、贈与せずにそのまま親が保有していたら家賃や配当が親の預金を増やすことになりますが、子に移しておけば家賃や配当は子の預金の増加に寄与します。
相続税だけでなく所得税の節税になることもあるので収益を生む財産を保有している人は検討の余地があるでしょう。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00





