スマホ・パソコンの相続の注意点と手続きガイド
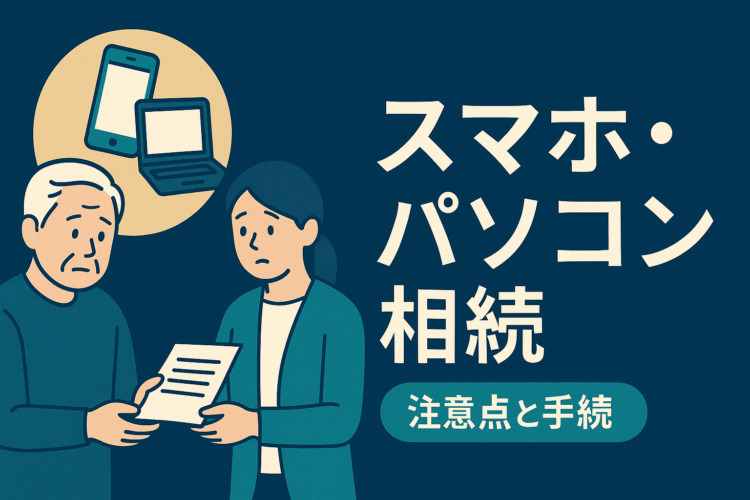
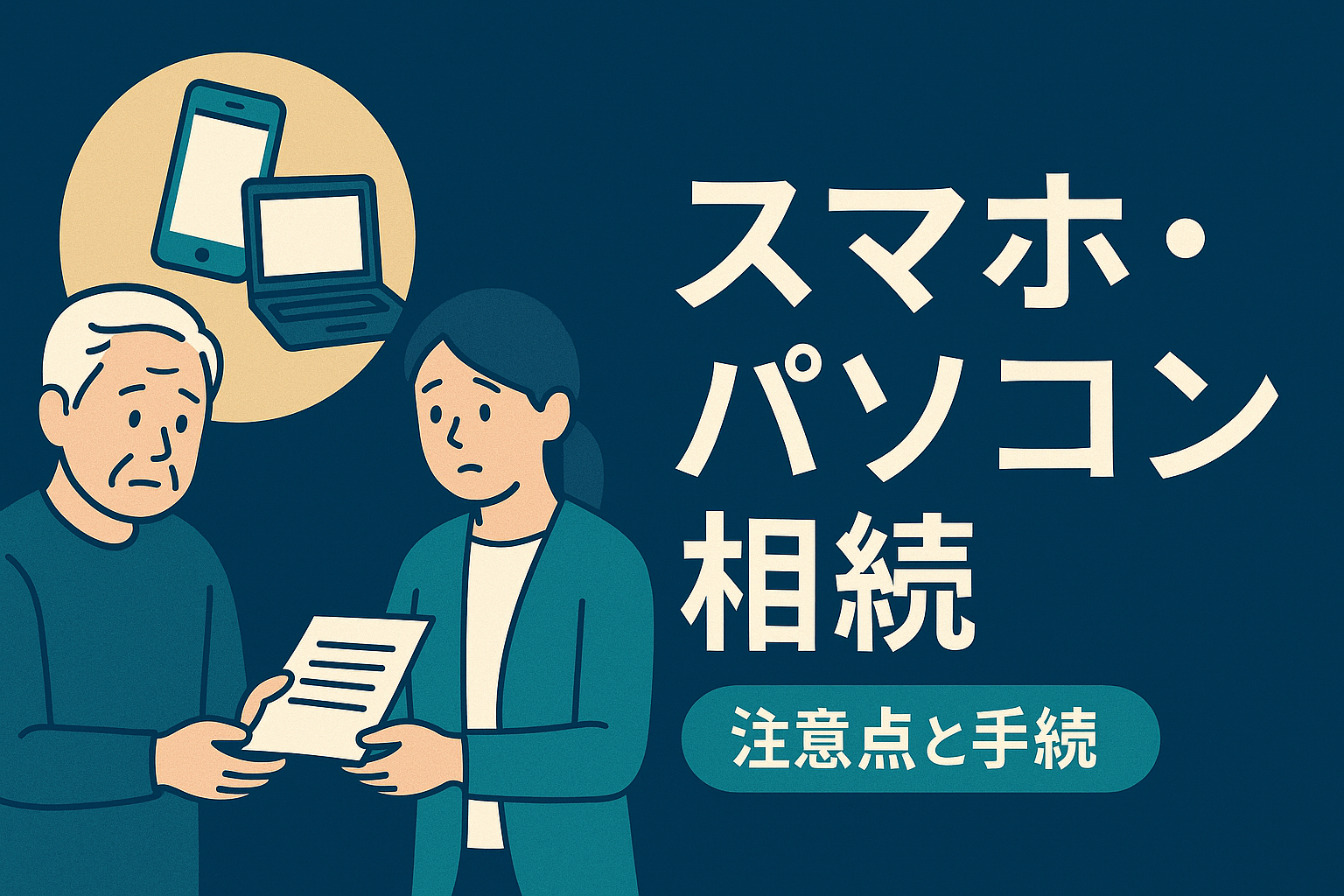
■パソコンとスマホに保存された情報は相続における重要な「デジタル遺産」である。
■パスワードやID情報へのアクセス方法を生前に家族と共有することが最優先事項。
■スマホやパソコン内に含まれるネット銀行口座、仮想通貨、電子マネーなどの財産は相続税の課税対象。
■相続人が不正アクセスに該当しないよう、被相続人の死亡後に必ず相続人による適切な手続きを取ること。
■デジタル遺品の発見遅れにより、後日の税務調査時に予期せぬ追徴課税が生じる可能性がある。
現代の生活において、パソコンやスマートフォンは単なる通信ツールではなく、財産や個人情報を管理する重要な媒体となっています。
総務省の調査によると、スマートフォンの世帯普及率は9割を超えており、ほとんどの家庭でスマホが使用されています。
ネット銀行口座、仮想通貨、電子マネー、クレジットカードのポイント、写真や動画などの個人データ、そしてSNSアカウントなど、被相続人の財産と個人情報の大部分がデジタル機器内に存在する時代となりました。
にもかかわらず、相続の際にこれらのデジタル情報にアクセスできなくなると、相続税申告の漏れ、財産の発見遅れ、不適切な税務申告、サブスク解約不能といった深刻な問題が生じます。
特に問題なのは、デジタル遺産の存在に相続人が気づかないまま相続手続きを終えてしまい、数年後の税務調査で追加納税を命じられるケースです。
本記事では、パソコンとスマホという現代の相続では避けて通れない課題について、具体的な対策方法と税務上の注意点を解説します。
目次
パソコンとスマホに隠された「見えない相続財産」
相続税の課税対象となる財産
パソコンやスマートフォンに保存または利用できる財産には、相続税の課税対象となるものが数多く存在します。
| 財産の種類 | 具体例 | 相続税対象 |
| ネット銀行口座 | 楽天銀行、住信SBIネット銀行など | 〇 相続税対象 |
| ネット証券口座 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券など | 〇 相続税対象 |
| 暗号資産 (仮想通貨) |
Bitcoin、Ethereum、その他のコイン | 〇 相続税対象 |
| 電子マネー | Suica、Paypal、Apple Pay、Google Pay等 のチャージ残高 |
〇 相続税対象 |
| マイレージ | JALマイル、ANAマイル等 | 〇 相続税対象 |
| クレカポイント | クレジットカード、百貨店のポイント | △ 契約次第 |
ネット銀行、ネット証券、仮想通貨、電子マネーなど、パソコンやスマホを通じてのみアクセスできる財産は全て相続税の対象となります。
これらは通帳が存在しないため、相続人が存在を把握しにくいという特徴があります。
それぞれの財産種類別の詳しい解説は、下記コラムをご参照ください。
ネット口座、仮想通貨などのデジタル遺品と相続税
【仮想通貨(暗号資産)に相続税はかかる!】評価方法・評価額まとめ
【5分でわかる】仮想通貨(暗号資産)の相続手続きとポイントを解説
ビットコインの相続で110%課税?!
【電子マネーは相続可能】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説
【マイルは相続できる!】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説
相続税の課税対象外となるもの
一方、相続税の課税対象にならないデジタルデータもあります。
SNSアカウント(Facebook、Instagram、Twitter、TikTokなど)は、各社利用規約により譲渡・承継が制限されることが多く、アカウントそのものの承継は不可または限定的な運用(追悼化・データ提供等)にとどまるのが一般的です。
一方、投稿コンテンツ等の著作権(財産権)は相続の対象になり得ます(著作権法61条)。
対応は各プラットフォーム規約に従い個別確認が必要です。
また、クレジットカードのポイントやマイレージは利用規約で「保有者の死亡により消滅・失効する」と定めている企業が多いため、相続税の対象外となるものもあります。
パソコンとスマホの相続で発生する「4つの課題」
課題①:パスワードやID情報がわからない
パソコンやスマートフォンにはロック機能が搭載されており、パスワードやパターン、顔認証、指紋認証などで保護されています。
被相続人がこれらのロック解除方法を家族に伝えていない場合、相続人がこれらのデバイスにアクセスすることは極めて困難です。
パスワードが判明しないまま相続手続きを進めると、以下のような問題が発生します。
■仮想通貨が存在することに気づかないまま相続手続きを終え、数年後に税務当局から指摘を受けるケース。
■メールボックスやクラウドストレージに重要な財産情報が保存されたままになり、相続財産の計算が不完全になるケース。
なお、国税庁の見解によれば、相続人がパスワードを知っているか知っていないかは問わず、被相続人が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。
パスワード不明を理由に相続税課税の対象外にすることはできません。
重要:
オンラインサービス等の“特定認証”を不正に突破してアクセスすると不正アクセス禁止法(3条等)に触れる可能性があります。
端末ロックの物理解錠自体は同法の直接の対象ではなくても、他人のID・パスワードを無権限利用してクラウド・金融口座へ接続する行為は違法となり得ます。
相続人であっても適法化されるわけではないため、各事業者の相続手続で正規開示を受けてください。
課題②:デジタル遺産の所在が不明
実体のないデジタル資産は、相続人が相続開始直後に発見することが困難です。
被相続人の生前の会話で「ネット銀行を使っている」と聞いていない限り、その存在を知る手がかりがありません。
スマートフォンにインストールされたアプリを見ても、デジタル資産の全容を把握することは不可能です。
その結果、相続手続きを終えた後に「実は仮想通貨を大量に保有していた」「ネット証券口座に株式が残っていた」ということが判明し、相続税申告のやり直しが必要になるケースが多発しています。
被相続人が相続財産のリストを作成していない場合、相続人は下記の手掛かりから地道に調査する必要があります。
■クレジットカードの利用履歴や引き落とし口座の入出金記録。
■確定申告書の控え(雑所得として計上された仮想通貨や証券の売却益)。
■PCやスマホのブラウザ履歴やブックマーク。
この場合、本来支払うべき相続税に加えて、加算税、延滞税のペナルティが課されるため、相続人の経済的負担が大幅に増加します。
相続税のペナルティについての詳しい解説は、相続税のペナルティ 加算税、延滞税の税率と計算方法 かからないケースもあり?!をご参照ください。
課題③:相続手続きが複雑で時間がかかる
ネット銀行やネット証券、仮想通貨取引所の相続手続きは、各金融機関によって異なります。
また、多くの場合、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など、複数の書類が必要です。
さらに、金融機関との連絡はメールやオンライン上でのやり取りが中心となるため、直接の対面手続きが可能な一般の銀行よりも手続き期間が長くなる傾向があります。
一般的には、相続手続き開始から金銭の払い戻しまで数ヶ月を要するケースが多いです。
課題④:サブスクの解約ができなくなる
被相続人が契約していた下記のような各種サブスクについて相続による解約が必要となります。
1. エンタメ系(月額利用型)
Spotify、Netflix、YouTube Premiumなど。亡くなった後も自動課金されるため特に注意が必要です。
2. ストレージ・バックアップ系
iCloud、Google Driveなどは解約だけでなく、保存データの引継ぎも重要。バックアップを取らずに削除依頼すると大切な写真が失われます。
3. ソフトウェア・アプリ系
Adobe、Microsoft 365などのサブスクは法人名義との混同が起きやすい領域。業務データの引継ぎを忘れずに。
4. デジタル金融系
証券アプリ、仮想通貨取引所、クラウドバンクなども「自動課金」の一種に含まれます。これらは金銭資産に直結するため、優先確認対象です。
上記のようなサブスクを解約する前に被相続人のネット回線やスマホを解約してしまうと解約遅延による継続課金リスクに陥ってしまう可能性もあるので手続きの順番には注意をしましょう。
詳しい解説は、相続でサブスク地獄!? 遺族がやるべき順序と注意点をご参照ください。
パソコンとスマホの相続に向けた生前準備
デジタル資産リストの作成
相続対策として最も重要なのは、生前にデジタル資産の存在を家族に伝え、リスト化しておくことです。
以下の情報を紙またはデジタルファイルにまとめて、安全に保管することをお勧めします。
エンディングノートまたはデジタル終活ノートに、以下の情報を記載します。
利用しているアプリ名(暗号資産取引所、電子マネーサービスなど)。
各サービスの登録メールアドレス。
大まかな残高や保有資産(正確な金額でなくても構いません)。
このリストには、必ずしもパスワードを記載する必要はありません。
パスワードを紙に書くことはセキュリティリスクが高いため、パスワード管理アプリを使用し、マスターパスワードのみを信頼できる家族に伝える方法が効果的です。
| 金融機関 | 口座番号 | 登録メール | 残高目安 |
| 楽天銀行 | ×××××××× | △△△@gmail.com | ○○○万円 |
| SBI証券 | ×××××××× | △△△@gmail.com | ○○○万円 |
| Coincheck | ×××××××× | △△△@gmail.com | Bitcoin ××枚 |
パスワード管理とアクセス方法の共有
パスワード管理には、1Password、Bitwarden、LastPassなどの専門的なパスワード管理アプリの使用をお勧めします。
多くのパスワード管理アプリには「緊急アクセス機能」が搭載されており、設定者が亡くなった後、指定した家族がマスターパスワードを入力して全てのアカウント情報にアクセスできるようになっています。
マスターパスワードは、信頼できる配偶者または成人した子どもに伝えておくのが良いでしょう。
なお、マスターパスワード自体は紙に書いて金庫に保管し、エンディングノートにその保管場所を明記しておくと安全です。
スマートフォンやパソコン自体の保管方法
被相続人のスマートフォンやパソコンは、相続手続きが完了するまで、相続人により安全に保管される必要があります。
相続人が無断でこれらのデバイスを破棄したり、リセットしたりすると、デジタル遺産へのアクセス手段が失われてしまいます。
また、被相続人が使用していたスマートフォンやパソコンを相続人が自分用に転用することも、セキュリティ上の理由から避けるべきです。
被相続人の生前にデジタル資産リストが作成されている場合でも、各金融機関への相続手続きにおいて、デバイスが必要になることがあります。
例えば、二段階認証が設定されているアカウントの場合、相続人がそのデバイスにアクセスできなければ認証ができず、相続手続きが進まなくなります。
被相続人が亡くなった後の対応手順
ステップ①:デジタル遺産の調査
被相続人が亡くなった直後から、相続人は下記に掲げるような方法でデジタル遺産を調査します。
その1:スマートフォンやパソコンへのアクセス
デジタル資産リストが存在する場合は、そのリストに基づいて調査を進めます。
リストが存在しない場合は、被相続人のスマートフォンやパソコンに保存されたメールボックスを確認し、金融機関からの利用明細や月次レポートを探します。
注意:
被相続人からパスワードを伝えられていた場合でも、そのID・パスワードを相続人が無断で使用して故人のアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に該当するリスクがあります。
ロック解除を試みること(アタック行為)だけでなく、正規の権限なくログインする行為自体が問題となります。
その2:クレジットカードや銀行の利用履歴から追跡
被相続人の通常の銀行口座やクレジットカード明細から、デジタル金融機関への送金記録を探します。
例えば、毎月「○○銀行」への送金があった場合、そのネット銀行にアカウントを持っている可能性があります。
その3:確定申告書の控えの確認
被相続人が確定申告していた場合、申告書の「雑所得」の項目を確認します。
仮想通貨の売却益や暗号資産の益出が記載されている場合、被相続人が暗号資産を保有していたことが判明します。
その4:郵便物やメール通知の確認
金融機関が定期的に送付している「報告書」や「取引確認書」のほか、金融機関からのメール通知も確認します。
その5:相続人以外の信頼できる者(弁護士や税理士)に相談
デジタル遺産の調査が自分たちでは困難な場合は、税理士や弁護士に相談し、法的な観点からサポートを受けることをお勧めします。
ステップ②:各金融機関への相続手続き
デジタル遺産が判明したら、各金融機関に相続の発生を報告し、正式な相続手続きを開始します。
| 相続手続きの種類 | 必要な書類 | 期間目安 |
| ネット銀行の相続 | 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書 | 1~3ヶ月 |
| ネット証券の相続 | 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書 | 1~3ヶ月 |
| 暗号資産の相続 | 戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、残高証明書依頼 | 2~6ヶ月 |
ステップ③:必要書類の準備
各金融機関の相続手続きに必要な書類は概ね共通しています。
これらの書類の取得には時間と手数料がかかるため、相続開始直後から計画的に進める必要があります。
詳しい書類の集め方については、相続税申告の必要資料・添付書類の一覧、効率的な収集方法をご参照ください。
パソコンとスマホの相続における税務上の注意点
ネット銀行やネット証券の相続と相続税
ネット銀行の預金やネット証券の株式は、相続開始日の時点での残高(または評価額)が相続税の課税対象となります。
評価方法は一般の銀行口座や証券口座と同様です。
相続開始日の残高証明書を金融機関に請求し、その金額をもとに相続税申告書に記載します。
暗号資産(仮想通貨)の相続と相続税
仮想通貨の相続税評価は、国税庁によって以下のように定められています。
被相続人が取引を行っていた暗号資産交換業者が公表する相続開始日の売却価格。
活発な市場が存在しない場合:
取引実態や市場状況に基づいて、個別に評価します。
暗号資産の相続については、【仮想通貨(暗号資産)に相続税はかかる!】評価方法・評価額まとめをご参照ください。
重要な注意点:
暗号資産を相続して売却した場合、相続税だけでなく所得税も課税されます。
最大110%の税負担が生じる可能性があるため、生前からの対策が重要です。
詳しくはビットコインの相続で110%課税?!の記事をご参照ください。
電子マネーやクレカポイントの相続と相続税
電子マネーの残高は相続開始日時点での金額が相続税の対象となります。
詳しい解説は、【電子マネーは相続可能】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説をご参照ください。
一方、クレジットカードのポイントやマイレージについては、利用規約で「会員の死亡により失効する」または「相続を認めない」と規定されている場合、相続人はその権利を行使できないため、相続財産とはならず課税対象外です。
ただし、規約上、相続人への承継・行使が認められている場合は、死亡時点の交換可能価額(または割引相当額)で評価した金額が課税対象となります 。
また、マイルについては相続の対象となるケースが多いようです。
詳しい解説は、【マイルは相続できる!】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説をご参照ください。
被相続人が亡くなった後、やってはいけないこと
スマートフォンやパソコンの無断処分・リセット
被相続人のスマートフォンやパソコンを、相続手続きが完了する前に勝手に売却したり、初期化してしまったりすることは絶対に避けてください。
デジタル遺産へのアクセス手段を失うだけでなく、後の相続税申告で必要な情報が失われてしまいます。
不適切なアカウントアクセス
被相続人がパスワードを家族に伝えていない場合、相続人が何度もパスワード推測でログインを試みることは避けてください。
不正アクセス禁止法に該当する可能性があるだけでなく、セキュリティ対策によってアカウントがロックされるリスクもあります。
代わりに、金融機関に「相続人である」ことを証明して、正規の相続手続きを進めることが重要です。
相続税申告書の不提出
デジタル遺産が判明したにもかかわらず、相続税申告書に記載しないで提出することは重大な脱税行為です。
後日、税務調査で発見されると、本来の相続税に加えて、重加算税(最大40%)や延滞税が課されます。
デジタル遺産の発見が遅れた場合は、速やかに修正申告を行い、追加納税の手続きをとることが重要です。
Q&A:よくある質問
Q:パスワードが不明でも相続税は課税されますか。
A:はい。
国税庁の見解によれば、パスワード不明を理由に相続税課税の対象外にすることはできません。
被相続人が保有していたデジタル資産は、パスワードの有無に関係なく相続税の課税対象となります。
ただし、各金融機関では、パスワードが不明でも相続人が身分を証明すれば相続手続きを進められるよう対応しています。
Q:スマートフォン自体は相続財産に含まれますか。
A:スマートフォンやパソコン自体の機械は、一般的に相続税の課税価格に大きく影響しない動産として評価されます。
中古品としての価値は低いため、相続税申告では家庭用財産一式に含めて評価することがほとんどです。
ただし、デバイス内に保存されたデジタル資産(写真、動画、NFTなど)に価値がある場合は、個別に評価が必要な場合もあります。
Q:被相続人のメールアカウントにアクセスするのは違法ですか。
A:相続人であっても、被相続人のID・パスワードを使用して正規の権限なくアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に該当する可能性があります 。
これは「パスワードなしで」アクセスする(アタック行為)場合に限られません。
故人の財産調査という目的であっても、メールプロバイダが定める正規の相続手続き(データの開示請求など)を経るのが法的に安全な手段です。
Googleアカウントの場合、Googleアカウント復旧サービスを利用できます。
Q:相続人全員でパスワード情報を共有する必要がありますか。
A:全員で共有する必要はありませんが、代表相続人や信頼できる1~2人が持っておくことをお勧めします。
複数人で共有すると、情報漏洩やセキュリティ上のリスクが高まります。
パスワード管理アプリの「緊急アクセス機能」を活用して、必要な時のみアクセスできる仕組みを作ることが効果的です。
Q:遺産分割協議でパソコンやスマホをどちらかの相続人に譲ることはできますか。
A:可能ですが、相続手続きが完全に完了した後にしてください。
特に暗号資産の手続きなど、複数人の署名や印鑑が必要な場合もあるため、焦らず進めることが重要です。
まとめ:パソコンとスマホの相続は生前準備が全て
現代の相続では、パソコンやスマートフォンという物理的な媒体に、多くの財産情報と個人情報が集約されています。
被相続人がこれらのデバイスへのアクセス方法を家族に伝えていない場合、相続手続きは著しく複雑化し、時間と費用がかかるようになります。
さらに深刻なのは、デジタル遺産の存在に気づかないまま相続手続きを終えてしまい、後日の税務調査で追加納税を命じられるケースが増加していることです。
最優先事項は、生前のうちにデジタル資産リストを作成し、パスワード管理方法を家族と共有することです。
エンディングノートに、利用している金融機関名、アプリ名、登録メールアドレスを記載し、パスワード管理アプリのマスターパスワードを信頼できる家族に伝えておきましょう。
この簡単な準備が、相続人の負担を大幅に軽減し、後の相続税申告を正確に進めるための基盤になります。
また、相続手続きが複雑な場合や、デジタル遺産の調査が困難な場合は、税理士や弁護士の専門家に相談することをお勧めします。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00






